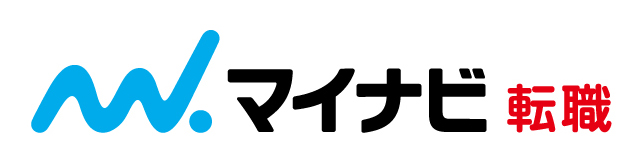BLOG
2025.09.29
新渡戸稲造「武士道」読書感想文
こんにちは。経営管理部の本多です。
今回は、日本人なら誰しも聞いたことがあるであろう著名な書である「武士道」(著:新渡戸稲造、訳:岬龍一郎、PHP文庫)を読んでみましたので、その感想を記します。ちなみに、読了までにかかった時間はおよそ3時間弱でした。
まず本書の概要ですが、1899年(明治32年)、新渡戸がアメリカ滞在中に執筆しました。当時の日本に対する海外の誤解を解き、日本の伝統的精神をあらわすものとして「武士道」を広く世界に紹介するために英語で書かれています。
また、「武士道」という思想自体は封建制度が始まった頃から発生し、仏教や神道、孔子の教えなども取り入れながら醸成されていったわけですが、あくまで倫理観や道徳観として口伝や伝承などを通じて、いわゆる掟として伝わってきたものであり、教科書的な書物はありませんでした。
江戸時代の書籍「葉隠」など、武士道について触れた書物はあったようですが、武士道を体系的に捉え、日本人全体の精神を表した思想書としては、この新渡戸著の「武士道」が唯一と言われています。

前置きはさておき、ここからが感想です。
本書を読み、ひと通り武士道について理解をした上で感じたのは、封建制度が崩壊してから今日で約150年ほど経ちますが、現在でも言われる日本人らしさ、日本人の良いところ、というのは武士道精神に基づいているものが多いということです。
もちろん当時と比べると、死生観や価値観、文化なども大きく異なっていますので、今では当てはまらない部分も多々ありますが、やはり武士道精神というものはどういうものなのか、日本人として理解しておくべきであり、かつ忘れてはいけないものは後世に伝えていかないといけないと感じました。
本書の中で心に残った箇所をいくつかご紹介します。
武士道は知識を重んじるものではない。重んずるものは行動である。
「義」は、武士の掟の中で、最も厳格な徳目である~義は自分の身の処し方を道理に従ってためらわずに決断する力である。死すべきときには死に、討つべきときには討つことである。
礼の最高の形態は、ほとんど愛に近づく。それは私たちにとって敬虔な気持ちをもって、「礼は寛容にして慈悲深く、人を憎まず、自慢せず、高ぶらず、相手を不愉快にさせないばかりか、自己の利益を求めず、憤らず、恨みを抱かない」ものであるといえる。
嘘をついたり、ごまかしたりすることは、卑怯者とみなされた。武士は支配者階級にあるだけに、誠であるかどうかの基準を、商人や農民よりも厳しく求められた。
名誉という感覚には、人格の尊厳と明白なる価値の自覚が含まれている。名誉は武士階級の義務や特権を重んずるように、幼児の頃から教え込まれ、武士の特質をなすものの一つであった。~「笑われるぞ」「名を汚すなよ」「恥ずかしくはないのか」といった言葉は、過ちを犯した少年の振る舞いを正す最後の訴えであった。
武士道は、一方において不平不満をいわない忍耐と不屈の精神を養い、他方においては他者の楽しみや平穏を損なわないために、自分の苦しみや悲しみを外面に表さないという、礼を重んじた。
「日本人以上に忠実で愛国的な国民がほかにいるだろうか」とは、このとき世界の多くの人々が発した問いであるが、私は誇りをもって「否」と答えることができる。
本書が執筆された当時というのは封建制度が崩壊しサムライがいなくなり、民主主義を始めとする西洋文化が日本に押し寄せた時代でした。
新渡戸稲造は本書の最後にこう記しています。
たしかに、武士道は独立した道徳体系の掟としては消え去るであろう。だが、その力はこの地上から滅び去るとは思えない。サムライの勇気や民族の名誉の学院は破壊されるかもしれないが、その光と栄光はその廃墟を超えて生きながらえるであろう。
外国人問題等に揺れる現代の日本においてこそ、本書は読んでおくべき一冊だと思います。
上記の斜体部分は「新渡戸稲造. いま、拠って立つべき“日本の精神” 武士道 (PHP文庫)」から引用しています。