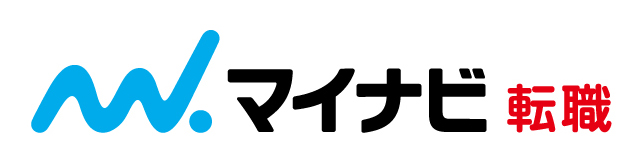Blog
BLOG
2018.06.11
ビジネスパートナー意見交換会報告 〜働き方改革〜
サービス&ソリューショングループの松末です。
初のブログ記事投稿です。今後ともよろしくお願いいたします。
私は、現在、メーカー系ソフトウェア開発会社に常駐して、システムの開発支援を行っています。
先日、取引先が主催する「ビジネスパートナー意見交換会」が行われました。

まずは、「事前に提示されていたお題目」について、ビジネスパートナー各社の責任者がスピーチを順番に行っていく形で始まりました。
事前に提示されていたお題目は、
- 働き方改革に関する各社の取り組み
- 職場環境について
というものでした。
働き方改革で、まず最初に出てくるキーワード「テレワーク」については、制度を導入している会社はあるものの、なかなか使用されていないのが実情です。
我々の仕事は、個人情報など秘密事項を扱うことが多いため、セキュリティ面がネックになっているということもあると思います。
(現状は、自宅で仕事をすると、一気に脅威や危険性が高まる可能性がります。)
この点については、クラウドに作業拠点を置き、そこから物を持ち出さないことで、ある程度、解消できます。
環境やサービスが整いつつありますので、実現可能な状況になってきていると思います。

次に、どの会社も「残業削減」や「休暇取得率アップ」というところの改善については、共通した認識を持っているようでした。ただ、実際のところ、改善はしているが、改革レベルまでには達していないというのが実情のようです。
担当業務でできる範囲内での効率アップだけでは、成果を重視しないといけないため、「改善の域からなかなか出られない」ということだと思われます。
改革レベルの領域に達するには、効率を上げて確保した時間を別のこと(新たな事業、取り組みなど)に使い、相乗効果でさらなるアップを目指すしかないのかもしれません。
その他の制度的なものとしては、
サンビット株式会社では、昨年、「ボランティア休暇制度」ができたことを紹介してきました。
まだ、使用された実績がないというのを付け加えなければいけなかったのが残念でした。
個人的には、この制度には、いろんな可能性が含まれていると感じています。
まずは、身近なところから改善して、そこで得た経験、情報などをヒントに別のことにも応用していこうところが良いです。
機会があれば、積極的に使いたいと考えております。(使用した際には、ブログで報告させていただきます。)
担当のプロジェクト内においては、改革レベルに到達できるように、引き続き、現場での改善活動に取り組んでいきたいと、スピーチの中で宣言させていただきました。
具体的な取り組みとしては、
チーム内の情報共有のためのホームページがあるのですが、そのホームページのスケジュール機能に、仕事や有給休暇の予定だけでなく、PTAなどの地域活動の予定や、参加する地域の祭りなどイベントの予定も書きこんでみることにしました。

2つ目のお題の「職場環境について」ですが、
お題として「ざっくり」としていたためか、これについての意見があまりでませんでした。
主催者側としては、「コンプライアンス的なところを考慮して、フロア内の席の配置の見直しなどを実施しているが、そのような点について仕事がやりずらくなったことなどがないのか」というのが意図だったようです。
そんな中で、唯一、気になった意見としては、
仕事の谷間などで、主力メンバーがプロジェクトを抜けざるを得ない状況になった場合に、一度、抜けてしまうと、タイミングによっては、そのプロジェクトには戻ることができなくなってしまうというものでした。
そういう時は、他部門の仕事で間をつなぐなど、1つのプロジェクトを長く続けられるような協力をしてほしいということでした。
この意見は、働き方改革にも関連する重要なポイントではないかという気がしました。
支援タイプの契約の場合、人月という単位での契約となります。その場合、仕事の大小に関係なく、契約する側は、人の拘束に対して対価を支払わなければいけません。契約を受ける側も成果の大小に関係なく時間を拘束されることになります。
そのような契約が主流であるため、ある意味、しょうがない話ではあるのですが。。。
今後、ますます、仕事はあるものの技術者が不足するという状況が予想され、生産性向上など、仕事の質を上げていく必要がでてきます。
ただ、仕事の質は、最終成果物だけを見てもわかりにくいものです。
人(人月)や物(プログラムなど)に対してだけの契約ではなく、今後は、仕事の質やサービスなど目に見えにくい付加価値的なことでも契約できるように、業界自体の改革が必要なのではないかと感じました。
現状としては、働き方改革に関する制度ができても、それを実際に使う現場との間には、まだ、すこし溝があるようです。
その溝を埋めるのも、システムエンジニアの役割なのかもしれません。
最近のエントリー
"寝る"以外の科学的な休養法
2026.01.19
疲れたときは「寝る」だけで十分だと思っていませんか?本記事では、科学的な視点から休養を7つのタイプに分類し、運動や人との交流、環境の変化など、行動することで回復につながる方法を紹介しています。自分に合った休養の取り方を知り、日々の疲労と上手に付き合うためのヒントをお届けします。
ラージボール卓球 ~2025年度 さがねんりんピックラージボール卓球交流大会~
2026.01.14
2025年10月に開催されたさがねんりんピック2025 ラージボール卓球交流大会に混合ダブルスA級で参加した体験を振り返ります。予選リーグを2位で通過し、決勝トーナメントでは準決勝まで進出。苦手とするカットマンペアとの対戦を通じて、戦術理解や練習の重要性を実感しました。結果だけでなく、試合を通して感じた反省や今後の反省、健康と向き合いながら競技を続けていく思いについても触れています。
2026年頭のご挨拶
2026.01.05
新年のご挨拶として、2025年の出来事を通じて感じた社会の変化や、これからの時代に求められる姿勢についてお伝えします。世界情勢、日本の政治、物価や農業の課題、そして不正に対する社会の目の厳しさなど、幅広いテーマを取り上げながら、企業として、個人として何を大切にすべきかを考えました。丙午の年を迎え、前向きな決意と未来への思いについて記しています。
カテゴリーリスト
アーカイブ
- 2026年01月(3)
- 2025年12月(5)
- 2025年11月(7)
- 2025年10月(4)
- 2025年09月(8)
- 2025年08月(6)
- 2025年07月(7)
- 2025年06月(7)
- 2025年05月(7)
- 2025年04月(6)
- 2025年03月(8)
- 2025年02月(6)
- 2025年01月(6)
- 2024年12月(7)
- 2024年11月(7)
- 2024年10月(6)
- 2024年09月(8)
- 2024年08月(6)
- 2024年07月(8)
- 2024年06月(6)
- 2024年05月(7)
- 2024年04月(7)
- 2024年03月(7)
- 2024年02月(8)
- 2024年01月(8)
- 2023年12月(9)
- 2023年11月(9)
- 2023年10月(8)
- 2023年09月(7)
- 2023年08月(8)
- 2023年07月(9)
- 2023年06月(8)
- 2023年05月(7)
- 2023年04月(6)
- 2023年03月(6)
- 2023年02月(6)
- 2023年01月(6)
- 2022年12月(6)
- 2022年11月(6)
- 2022年10月(7)
- 2022年09月(6)
- 2022年08月(7)
- 2022年07月(6)
- 2022年06月(7)
- 2022年05月(7)
- 2022年04月(6)
- 2022年03月(6)
- 2022年02月(6)
- 2022年01月(7)
- 2021年12月(6)
- 2021年11月(7)
- 2021年10月(6)
- 2021年09月(6)
- 2021年08月(7)
- 2021年07月(6)
- 2021年06月(6)
- 2021年05月(7)
- 2021年04月(6)
- 2021年03月(7)
- 2021年02月(6)
- 2021年01月(6)
- 2020年12月(6)
- 2020年11月(6)
- 2020年10月(5)
- 2020年09月(4)
- 2020年08月(5)
- 2020年07月(5)
- 2020年06月(5)
- 2020年05月(4)
- 2020年04月(4)
- 2020年03月(6)
- 2020年02月(4)
- 2020年01月(4)
- 2019年12月(4)
- 2019年11月(4)
- 2019年10月(4)
- 2019年09月(5)
- 2019年08月(2)
- 2019年07月(5)
- 2019年06月(4)
- 2019年05月(3)
- 2019年04月(5)
- 2019年03月(4)
- 2019年02月(4)
- 2019年01月(4)
- 2018年12月(4)
- 2018年11月(4)
- 2018年10月(5)
- 2018年09月(4)
- 2018年08月(4)
- 2018年07月(5)
- 2018年06月(5)
- 2018年05月(4)
- 2018年04月(5)
- 2018年03月(5)
- 2018年02月(6)
- 2018年01月(5)
- 2017年12月(5)
- 2017年11月(4)
- 2017年10月(4)
- 2017年09月(2)
- 2017年08月(3)
- 2017年07月(1)
- 2017年05月(2)
- 2017年04月(5)
- 2017年03月(5)