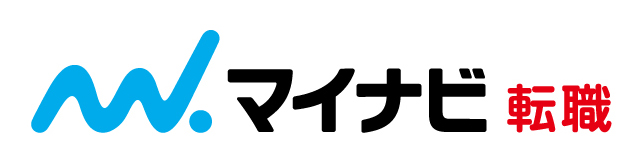BLOG
2025.03.03
「なぜ倒産、運命の分かれ道」について
代表の中野です。
「倒産」——
経営者や社員にとって、これほど忌まわしい言葉はありません。
2025年1月の企業倒産件数は830件にのぼり、前年同月比で18.6%の増加となりました。これで33ヶ月連続して前年同月を上回っています。
倒産増加の背景には、ゼロゼロ融資の返済負担、人手不足、物価高など、さまざまな要因が影響しています。
当然のことながら、倒産を望む経営者や社員はいません。
では、なぜ企業は倒産してしまうのでしょうか?
倒産する会社の傾向を探るべく、本年2月に出版された
「なぜ倒産、運命の分かれ道」(帝国データバンク情報統括部)
を読みました。
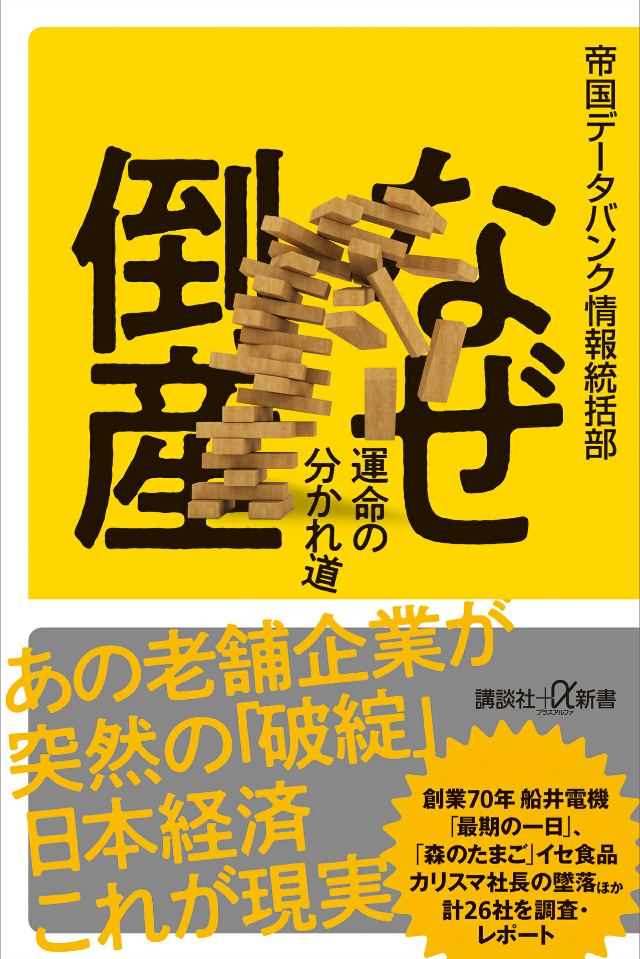
この書籍では、26社の倒産事例が紹介されています。
業種は多岐にわたりますが、どの事例も非常に参考になります。
特に注目したのが「新電力業界」の事例です。
2016年の自由化を皮切りに、新電力市場は急成長を遂げました。
しかし、2020年末からのエネルギー価格高騰により、電力調達コストが急増し、多くの新電力会社が「逆ザヤ」状態に陥りました。
一時期は700社もの新電力会社が乱立しましたが、2024年3月時点で119社が倒産または事業撤退しています(帝国データバンク資料より)。
参入者が多い事業には思わぬ落とし穴があることを、この事例は示してくれます。
書籍では、新電力業界以外にも、以下のような倒産事例が紹介されています。
- 富士通のらくらくホンを引き継いだ端末メーカー
- 少年野球帽を製造していた老舗企業
- 国内最大級の規模を誇っていた矯正歯科
- スキューバダイビング専門の出版社
環境変化に適応できず倒産した事例も少なくありません。
経営者にとって、変化に対応する力がいかに重要であるかを痛感させられます。
また、業種や規模を問わず、倒産企業に散見されるのが「粉飾決算」です。
粉飾決算とは、実態よりも見た目を良く見せるために数字を操作することを指します。
では、なぜ経営者は粉飾を行うのでしょうか?
一つは過剰な成功志向や株主からのプレッシャーです。
成功を求めること自体は悪いことではありません。
しかし、第三者に定期的に自社の実力について、客観的に評価してもらう仕組みが必要です。
二つ目は強い虚栄心、自己顕示欲です。
オーナー経営者は、自身が大株主であるため、株主からの圧力はありません。
しかし、周囲の人々に対して見栄を張りたいとか 、過度なブランド志向によって実態以上に業績を良く見せようというケースは少なくないようです。
歴史作家の加来耕三氏は、次のように語っています。
「歴史が繰り返し語っていることは“油断大敵”です。今、敵が来たらどう逃れ、どう対処するか。我々は常にそれぞれの立場で考えておく必要があります」
この言葉は倒産はもとより、防災や経営全般にも通じる教訓です。
本書籍で紹介された数々の倒産事例を踏まえ、謙虚な心で歴史から学ぶ姿勢を忘れずにいたいと思います。